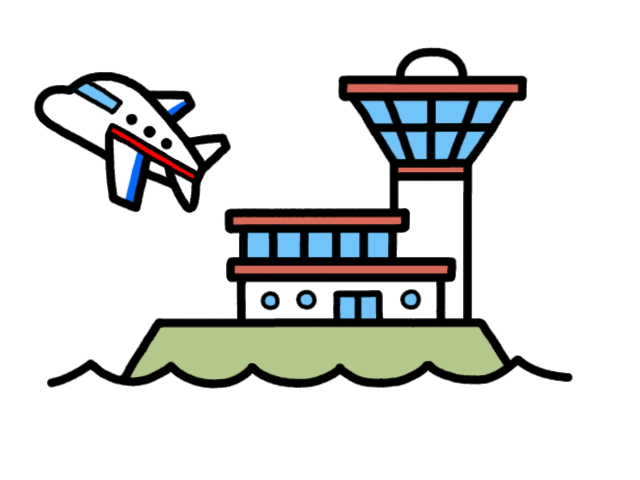航空管制と言えば何を思い浮かべますか?
きっと多くの方が管制塔、いわゆるタワーを思い浮かべるのではないでしょうか?
そしてタワーの中で飛行機を見ながら離着陸の指示を出しているのが管制官です。
ではもし、タワーがない空港があると聞いたらどうですか?
さらにタワーどころか管制官もいない空港があると聞いたら?
今回は空港の種類について紹介します。
管制塔がない空港、管制官のいない空港がある
エアラインの旅客機が離着陸するような空港では、大抵の場合管制塔があって、その中では航空管制官が管制業務を行っています。
旅客機の運航は特別な事情がない限り、常に航空管制官に監視され、管制官の指示や許可を得ながら飛ぶ方式が取られています。
これを専門的な用語で言うと、計器飛行方式と言います。
とりわけ空港周辺の飛行や空港内の地上走行では、多数の飛行機が密集するので管制官がタイミング見計らって離陸、着陸の許可を飛行機に対して出しています。
この離着陸の監視を行っている場所が管制塔であり、中で管制業務を行っているのは「タワー」というコールサイン(無線での呼び出し呼称)の航空管制官です。
ですが、実は運航便数の規模などによっては管制塔がなく、中で働く管制官がいない空港があったりするのです。
具体的には、空港は離着陸のための航空管制の種類に従って以下の3つに分類されます
① 航空管制官が担当する空港
② 航空管制運航情報官が現地で監視する空港
③ 航空管制運航情報官が遠隔監視する空港(旧リモート空港)
この3種類の空港がそれぞれどのように違うのか見ていきましょう。
空港の種類は3種類
航空管制官が担当する空港
まず始めが航空管制官が担当する空港で、いわゆる「空港」の中でもっともイメージが湧くであろう空港です。
空港には管制塔があって、管制塔の中では航空管制官が離着陸する飛行機を監視しています。
日本の空港でこの種別に分類される例が以下です。
・羽田空港 ・成田空港
・新千歳空港 ・函館空港
・秋田空港 ・仙台空港
・中部国際空港 ・伊丹空港
・関西国際空港 ・神戸空港
・高松空港 ・高知空港
・広島空港 ・福岡空港
・熊本空港 ・鹿児島空港
・那覇空港 などなど
主要な空港はもちろん、地方を含めて多くの空港がこれに該当します。
では、後に紹介する2種類の空港とは何が違うの?となるわけですが、簡単に言えば、これらの空港は「タワー」という管制席がある空港になります。
この「タワー」という語ですが、これは「管制塔」を意味しているわけではありません。
航空無線にはコールサインという呼び出し呼称があって、航空管制では離着陸や巡航などフェーズに応じて担当する管制官が異なり、それぞれ異なったコールサインで呼ばれます。
このうち、離着陸を担当する航空管制官のコールサインが「タワー」なのです。
タワーの管制官は管制塔から目視で飛行機を監視し、離着陸する飛行機に対して離着陸の許可を出しています。
航空管制のやり取りの例を挙げてみましょう。
離陸の時
「Japan Air XX, Wind 340° at 10, Runway 34 Cleared for Takeoff」
(Japan Air XX、風は340°から10kt吹いています、Runway34からの離陸を許可します。)
着陸の時
「All Nippon XX, Runway 16 Clear to Land, Wind 100° at 7 」
(All Nippon XX、Runway16への着陸を許可します、風は100°から7kt吹いています。)
この「Clear」という語が「~を許可する」を意味します。
例文のとおり、タワーの管制官は飛行機に対して離着陸の許可を管制塔から出しているのです。
画像は熊本空港ですが、ターミナルビルのすぐそばにタワーが建っており、中では航空管制官が業務を行っています。↓
 熊本空港のターミナルビルと管制タワー
熊本空港のターミナルビルと管制タワー・管制塔がある
・航空管制官が離着陸の許可を出している
・離着陸を担当する航空管制官には「タワー」のコールサインが使われる
航空管制運航情報官が現地で監視する空港
次は航空管制運航情報官が現地で監視する空港ですが、航空管制運航情報官はあまり馴染みのない言葉かもしれません。
これらの空港にも管制塔があって、中から離着陸する飛行機の監視がなされています。
ところが、管制塔にいる人は「航空管制運航情報官」と言って、航空管制官とは資格が違うのです。
この航空管制運航情報官も無線を使って飛行機とやり取りを行うのですが、その際のコールサインは「レディオ」が使用されます。
では先ほどの「タワー」とは何が違うのでしょうか?
最大の違いは
飛行機に対して許可や指示が出せるのか、情報提供しかできないのか
になります。
このような空港での運航情報官の業務を「飛行場対空援助業務」と言いますが、具体的な離着陸時の無線交信を見てみましょう。
Japan Air XX, Runway 30, Runway is Clear, Wind 280° at 5
(Japan Air XX、Runway30は滑走路上に障害物や他機がいません、風は280°から5kt吹いています。)
先ほどのタワーとのやり取りとは少し違いますね。
タワーでのClearは許可するの意味だったのですが、ここでの「Runway is Clear」というのは「滑走路上に障害物や他機がいないですよ」の意味になります。
2つのニュアンスを比べてどうでしょう?
レディオが使用される空港では状況を単に報告しているだけであって、良いとかダメとか指示的な言葉になっていないのです。
航空管制運航情報官は航空管制官と違って飛行機に対して指示や許可を出すことができない資格なのです。
つまり、本当に離着陸しても問題がないかどうかはパイロット自身が判断します。
日本の空港で航空管制運航情報官が現地で監視する空港の例は以下のとおりです。
・稚内空港 ・山形空港
・福島空港 ・松本空港
・静岡空港 ・出雲空港
・佐賀空港 など
比較的便数が少ない空港が該当していることが分かります。
このような空港では管制官を配置して飛行機に指示を与えなくとも、運航上支障がないというわけです。
下の画像は佐賀空港の管制塔ですが、管制塔の中にいるのは航空管制運航情報官で、コールサインはタワーではなく「レディオ」です。↓

・管制塔がある
・航空管制運航情報官が離着陸の情報提供を行っている
・航空管制運航情報官には「レディオ」のコールサインが使われる
航空管制運航情報官が遠隔監視する空港(旧リモート空港)
最後は航空管制運航情報官が遠隔監視する空港です。
これらの空港はなんと基本的に管制塔がなく、離着陸する飛行機を現地で監視している人はいません。
ではどうするかと言うと、近くの大規模空港にある専用センターで、監視モニターを使った遠隔監視が行われているのです。
この専用センターは新千歳、伊丹、福岡、鹿児島、那覇の5つの空港事務所にあり、それぞれ管轄のエリアが異なります。
ここで遠隔監視しているのは航空管制運航情報官で、現地の飛行機との無線交信も管轄の空港事務所から行っています。
この時のコールサインは「レディオ」で、無線のやり取りも先ほどの航空管制運航情報官が現地で監視する空港と同様です。
すなわち、飛行機に対して指示や許可ではなく、助言的な性格の情報のみが提供されるのです。
ところで、実はこの種の空港はかつて「リモート空港」と呼ばれ、コールサインも「リモート」が使われていました。
無線で聞かれる用語も独特で、以下のようなやり取りが行われていました。
旧リモート空港で聞かれた交信の例
All Nippon XX, Wind 330° at 5, Obstruction not Reported on Runway
(All Nippon XX、風は330°から5kt吹いています、滑走路上に障害物は報告されていません。)
ニュアンス的にあくまで間接的に空港の監視を行っている様子が伝わってきますね。
運航情報官の業務自体も「リモート対空援助業務」と定義されていたのですが、2021年10月より運用が変更され、先の航空管制運航情報官が現地で監視する空港(旧レディオ空港)と同様とみなされるようになりました。
つまり、コールサインが「レディオ」に統一され、使われる用語も統一されると共に、運航情報官の業務も「飛行場対空援助業務」に一元化されたのです。
少々ややこしい事情がありましたが、遠隔監視がなされている空港(旧リモート空港)の例は以下になります。
・紋別空港 ・中標津空港
・大館能代空港 ・庄内空港
・八丈島空港 ・鳥取空港
・対馬空港 ・種子島空港
・久米島空港 ・与那国空港 など
1日数便の空港であったり、離島の空港が多いのが分かります。
このような空港では、遠隔監視で十分に運航することが可能なのです。
下の画像は大館能代空港ですが、周辺にタワーらしき建物は見当たりません。↓
 大館能代空港を正面から
大館能代空港を正面から 大館能代空港の正面から左
大館能代空港の正面から左 大館能代空港の正面から右
大館能代空港の正面から右なお、例えば庄内空港も遠隔監視の空港になりますが、空港敷地内には管制塔があります。
こういったケースは大抵の場合、元々航空管制運航情報官が現地で監視する空港だったものが、遠隔監視に切り替わった後も建物が残っているということのようです。
・基本的に管制塔がない
・航空管制運航情報官が遠隔監視により離着陸の情報提供を行っている
・航空管制運航情報官には「レディオ」のコールサインが使われる
・かつては「リモート空港」と呼ばれ、コールサインも「リモート」が使用されていた
航空管制業務と飛行情報業務
最後に豆知識ですが、航空管制官は飛行機に対して指示や許可ができ、航空管制運航情報官は情報提供しかできないと言いました。
これについてもう少し詳しく説明すると、実はそれぞれの従事する業務も定義の上で明確に分かれているのです。
航空管制官の従事する業務は「航空管制業務」と言い、飛行機に対して指示や許可を出す仕事です。
一方、航空管制運航情報官の業務は「飛行情報業務」と言い、飛行機に対して情報提供をする業務で、先ほどの「飛行場対空援助業務」はこれに含まれるというわけです。
終わりに
いかがでしたか?
もしも航空管制を聞くのが趣味という方は、これらの空港での無線交信の違いに注目すると面白いですし、そうでない方も管制塔の有無に注目してみると面白いと思います。
身近な空港が3つのどれに該当するのか、調べてみてはいかがでしょうか?
以上!